「御朱印集めを始めると、かえって運気が下がる」という噂を聞いて、不安を感じていませんか。
インターネット上では、御朱印集めは良くないと噂がありますが本当ですか?という疑問の声や、神様同士が喧嘩する、御朱印帳は危険なものだ、といった少し怖い話まで見かけます。
さらには、ひどい対応をされた、初詣の御朱印は迷惑だ、といったネガティブな体験談もあり、御朱印を人に見せることの是非や、御朱印集めとスピリチュアルの関係性についても様々な意見が飛び交っています。
その結果、熱心に集めていたけれど、もうやめたという人もいるようです。
御朱印にはご利益があるのですか?という根本的な問いから、御朱印をもらった後はどうするのが良いか、御朱印帳を置いてはいけない場所はどこか、など、実践的な悩みも尽きません。
この記事では、これらの疑問や不安を一つひとつ丁寧に解き明かし、皆様が安心して御朱印と向き合い、運気アップに繋がるような心豊かな参拝ができるよう、その本質と正しい作法を徹底解説します。
この記事のポイント
- 御朱印で運気が下がると言われる本当の理由
- 神様や仏様に関する俗説の真相
- 運気を下げないための正しい参拝作法とマナー
- 御朱印帳の適切な保管方法と扱い方
「御朱印で運気が下がる」は本当?噂の真相
- ①御朱印集めは良くないと噂がありますが本当ですか?
- ②「神様は喧嘩する」という俗説と神仏習合の歴史
- ③御朱印帳が危険と言われるのは不敬な扱いのこと
- ④いただいた御朱印を人に見せるのはマナー違反?
- ⑤「ひどい御朱印」と感じてしまうのはなぜか
- ⑥御朱印集めをやめた人の意見から学ぶべきこと
①御朱印集めは良くないと噂がありますが本当ですか?
 運気アップ研究所:イメージ
運気アップ研究所:イメージ
結論から言うと、御朱印集めそのものが悪いわけではありません。
「御朱印を集めると運気が下がる」あるいは「良くないことが起きる」という噂の根源は、御朱印という「モノ」にあるのではなく、それをいただく際の私たちの「心構え」と「行動」にあります。
本来、御朱印は神社仏閣へ参拝した「証」として授与される神聖なものです。
しかし、近年のブームにより、この本質が見失われがちになっています。
例えば、以下のような行為は、神仏に対して失礼にあたり、結果として自らの運気を損なう原因となり得ます。
運気を下げるとされる主な行動
- スタンプラリー感覚での収集
神仏への敬意を忘れ、ただ数を集めることや珍しいデザインを手に入れることだけが目的になってしまう行為。拝殿で手を合わせず、真っ先に授与所へ向かうのは本末転倒です。 - 不敬な態度
「お金を払っているのだから客だ」という傲慢な態度や、書き手の方への無礼な言動、他の参拝者を顧みない振る舞いは、神聖な空間にふさわしくありません。 - 転売目的の入手
参拝せずに御朱印を手に入れる転売行為は、御朱印を単なる商品として扱う極めて不敬な行いです。寺社側も強く非難しています。
つまり、「運気が下がる」という噂は、こうした不敬な行いに対する警鐘であり、御朱印文化を守るための民俗的な自己防衛反応と解釈できます。
敬意と感謝の心を忘れなければ、御朱印集めが不運を招くことは決してありません。
②「神様は喧嘩する」という俗説と神仏習合の歴史
 運気アップ研究所:イメージ
運気アップ研究所:イメージ
「神社とお寺の御朱印を同じ御朱印帳にいただくと、神様と仏様が喧嘩する」という話を聞いたことがあるかもしれません。
これは、御朱印集めを始めたばかりの方が抱きやすい不安の一つですが、結論として、神様と仏様が喧嘩することはありません。
この俗説は、日本の長い信仰の歴史を知ることで解消されます。
神仏習合(しんぶつしゅうごう)
明治時代に神仏分離令が出されるまで、日本では千年以上もの間、「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」という信仰の形が一般的でした。
これは、日本の神々が仏教の守護神とされたり、仏が神の姿を借りて現れたと考えられたりするなど、神道と仏教が融合し一体として信仰されていた文化です。
そのため、歴史的に見れば、一つの帳面に神社とお寺の印が混在することはごく自然なことでした。
神様や仏様は、人間が考えるような嫉妬や対立といった感情を超越した、寛大で慈悲深い存在とされています。
分ける方が無難とされる現代的な理由
ただ、現代においては、ごく稀に厳格な方針を持つ寺社で、他の宗教の印がある御朱印帳への揮毫を断られるケースが報告されています。
このような予期せぬトラブルを避けるため、また、より丁寧な作法として「神社用」と「お寺用」で御朱印帳を分けることを推奨する専門家や経験者は多くいます。
これは神様が喧嘩するからではなく、あくまで現代における円滑なコミュニケーションのための配慮と言えるでしょう。
多くの神社仏閣はこの点を理解しており、混在していても快く授与してくださいます。
しかし、心配な方は分冊しておくと、より安心して御朱印巡りを楽しめます。
③御朱印帳が危険と言われるのは不敬な扱いのこと
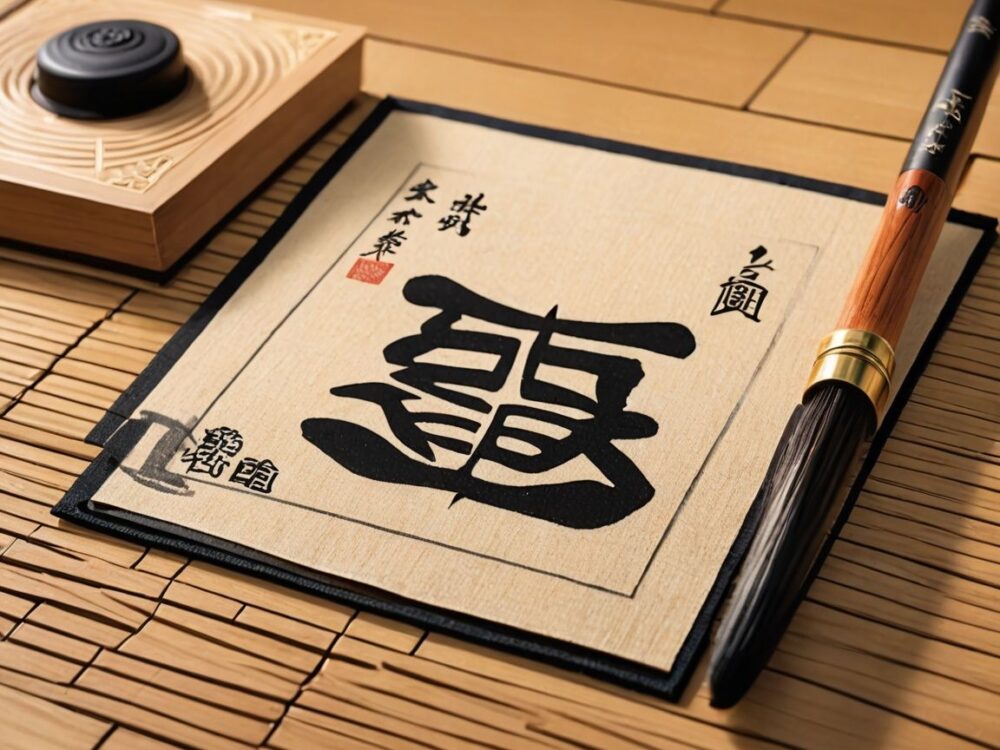 運気アップ研究所:イメージ
運気アップ研究所:イメージ
「御朱印帳は危険だ」という言葉も、字面だけ見ると非常に不安を煽るものです。
しかし、これも御朱印帳自体が呪物のように超自然的な危険を及ぼすという意味ではありません。
ここで言う「危険」とは、神聖なものを不敬に扱うことによって生じる、精神的・社会的な「危うさ」を比喩的に表現した言葉です。
具体的には、以下のような危険性が指摘されています。
1.精神的な危険性
神仏とのご縁を結ぶという神聖な行為が、単なる物集めの趣味に成り下がり、本来得られるはずだった心の安らぎや精神的な成長の機会を失ってしまう危険性です。
御朱印の数ばかりを気にして、参拝の感動や感謝の気持ちを忘れてしまうことは、魂にとっての「危険」と言えるかもしれません。
2.社会的な危険性
マナー違反の行動によって、寺社の方や他の参拝者との間に摩擦や対立を生み、不快な思いをする、あるいはさせてしまう危険性です。
これが「あの人は危険だ」という評判に繋がり、自分自身の社会的信用を損なうことにもなりかねません。
3.物理的な危険性
これは御朱印帳そのものに対する危険です。
御朱印帳は和紙でできているものが多く、雨や湿気、折れ曲がりに非常に弱いです。
カバンの中にそのまま入れたり、車内に放置したりすると、シミやカビ、色褪せの原因となります。
これを防ぐために、ビニールカバーや専用の袋で保護することが推奨されます。
御朱印帳が「危険」なのではなく、それを「ぞんざいに扱うこと」が危険なのです。
神聖なものを大切に扱わない心そのものが、運気を遠ざける原因になると考えましょう。
④頂いた御朱印を人に見せるのはマナー違反?
 運気アップ研究所:イメージ
運気アップ研究所:イメージ
頂いた御朱印を他の人に見せることについて、特に禁止する決まりはありません。
実際、多くの方がSNSなどで自身の御朱印帳を共有し、その美しさや旅の思い出を分かち合っています。
ここで最も重要になるのは、見せる際の「意図」です。
ポジティブな共有は、むしろ歓迎されるべき行為と言えます。
推奨される見せ方(共有)
自身の参拝の記録や御朱印の芸術性を伝えることで、見た人が「自分も参拝してみたい」と感じるきっかけを作るような共有は、神仏とのご縁をさらに広げる素晴らしい行いです。
「この神社の雰囲気がとても良かった」「このお寺のこの部分に感動した」といった体験談を添えることで、単なる画像以上の価値が生まれます。
一方で、好ましくないとされるのは、収集した数を自慢したり、他人の御朱印と比較して優劣をつけたりするような見せ方です。
避けるべき見せ方(自慢)
「こんなにレアな御朱印を持っている」「あなたよりたくさん集めている」といった、優越感に浸るための見せびらかしは、御朱印集めが不敬な「スタンプラリー」になっている証拠です。
このような心态は、御朱印の本質から外れており、運気を損なう原因と見なされても仕方ありません。
結論として、感謝と敬意の心をもって、ご縁の素晴らしさを分かち合うために見せるのであれば、何の問題もありません。
大切なのは、自慢や比較の道具にしないことです。
⑤「ひどい御朱印」と感じてしまうのはなぜか
 運気アップ研究所:イメージ
運気アップ研究所:イメージ
「期待していたデザインと違う」「文字が雑に見える」といった理由で、「ひどい御朱印をもらった」と感じてしまうことがあるかもしれません。
しかし、これは多くの場合、個人の主観的な期待と、寺社ごとの伝統や方針とのギャップから生じる感想です。
例えば、日本で最も格式高い神社の一つである伊勢神宮の御朱印は、非常にシンプルで、印と日付、寺社名のみで構成されています。
これを「手抜きだ」と感じるのは、近年のカラフルで華美な御朱印を見慣れた消費者的な視点からくる誤解です。
シンプルさこそが、その神社の古来からの伝統や様式の現れなのです。
「ひどい」のではなく「伝統」と捉える
一つひとつの御朱印は、その瞬間にその場所でしかいただけない、世界に一つの尊いご縁の証です。
書き手の筆致やデザインについて不満を述べたり、ネットで見た写真と違うと文句を言ったりするのは、御朱印の本質を理解していない行為であり、絶対にしてはいけません。
また、「ひどい対応をされた」「怒られた」という経験も、その原因をたどると、参拝者自身の行動に問題があるケースが少なくありません。
- 受付時間外に訪問している
- 御朱印帳ではなくメモ帳などを差し出している
- そもそも御朱印を授与していない宗派の寺院(例:浄土真宗など)で強要している
- 書き手を急かしたり、大声で話したりしている
御朱印は必ずもらえると保証された「商品」ではありません。寺社側の都合や、参拝者の態度によっては授与を断られることもあります。
そのような場合は、「今回はご縁がなかった」と潔く受け止め、日を改めて参拝するのが正しい心構えです。
⑥御朱印集めをやめた人の意見から学ぶべきこと
 運気アップ研究所:イメージ
運気アップ研究所:イメージ
御朱印集めは心豊かな趣味ですが、一方で「集めることに疲れてしまった」という理由で、やめたという人もいます。
この「御朱印疲れ」の原因の多くは、本来の目的を見失い、集めること自体が義務になってしまうことにあります。
手段が目的になる「スタンプラリー化」の弊害
月替わりや季節限定の御朱印が次々と登場する現代では、「あの限定御朱印を逃してしまった」「期間内にあそこへ行かなければ」といった焦燥感に駆られることがあります。
心の安らぎを求めて始めたはずの行為が、いつしか不安とプレッシャーに満ちたものに変わってしまうのです。
これは、収集という「手段」が、参拝という「目的」を乗っ取ってしまった典型的な例です。
このような精神的な燃え尽き(バーンアウト)は、とても残念なことです。
もし少しでも「疲れたな」と感じたら、一度立ち止まって「なぜ自分は御朱印集めを始めたのか」という原点に立ち返ってみましょう。
収集のプレッシャーから解放されると、本来の喜びが見えてきます。
神社の静かな森の空気、本堂の前で静かに祈る時間、その旅で出会った風景や人々との交流こそが、真の報酬のはずです。
御朱印帳は、そうした尊い瞬間を思い出すための「心のアルバム」です。
後から見返した時に、行列に並んだ記憶だけでなく、その日の天気や穏やかな気持ちが蘇るようなら、あなたの御朱印集めは正しい道を歩んでいます。
御朱印で運気が下がるのを避けるための作法Q&A
- ①そもそもご利益があるのですか?
- ②もらった後はどうするのが良いですか?
- ③御朱印帳を置いてはいけない場所と正しい保管方法
- ④初詣の御朱印が迷惑になるケースとは
- ⑤御朱印集めとスピリチュアルで目指す運気アップ
- ⑥まとめ:御朱印で運気が下がるは本当か?
①そもそもご利益があるのですか?
 運気アップ研究所:イメージ
運気アップ研究所:イメージ
「御朱印にご利益はありますか?」という問いに対して、多くの神職や僧侶は、御朱印そのものがお守りのように直接的な幸運をもたらすわけではない、と説明しています。
ご利益とは、御朱印という「モノ」を手に入れることによって得られるのではなく、そこに至るまでの「プロセス」―すなわち、聖地まで足を運び、心を静めて参拝するという行為―の中に宿るものなのです。
これは「資格試験の合格証書」に例えると分かりやすいでしょう。
本当に価値があるのは、合格証書という紙そのものではなく、そこに至るまでの学習の努力と合格したという事実です。
御朱印は幸運の「きっかけ」
しかし、御朱印集めを始めてから運が良くなったと感じる人がいるのも事実です。
これは、御朱印が幸運をもたらす「きっかけ」として機能しているためです。
御朱印をいただく目的で神社仏閣へ参拝する機会が増えると、清浄な空間に身を置くことで心身が浄化され、精神的な安定が得られます。
この心の状態の向上が、物事を良い方向へ導き、「運気が上がる」という体験に繋がるのです。
つまり、御朱印は幸運の源泉ではなく、幸運を引き寄せるための善い行いへの動機付けと言えます。
この本質を理解することが、心豊かな参拝への第一歩です。
②もらった後はどうするのが良いですか?
 運気アップ研究所:イメージ
運気アップ研究所:イメージ
御朱印をいただいた後の扱いは、参拝の延長線上にある大切な行為です。
御朱印帳は、自身の信仰の歩みを記した一生の宝物。その扱い方には、神仏への敬意が表れます。
1.生涯大切に保管する
一冊の御朱印帳がすべて埋まったら、それは「満願」となります。
感謝とともに新しい一冊を始め、満願した御朱印帳は自宅で大切に保管します。
時々見返すことで、参拝した時の気持ちを思い出し、信仰心を新たにすることができます。
2.副葬品として
自身の死後、御朱印帳を棺に入れてもらうことは、古くから行われている慣習の一つです。
特に寺院の御朱印は、生前に積んだ功徳の証として、あの世で閻魔様に見せることで極楽浄土へ導かれる、という信仰もあります。
3.やむを得ず手放す場合(お焚き上げ)
万が一、破損などでやむを得ず手放す場合は、決してゴミとして捨ててはいけません。
古いお守りやお札と同様に、神社やお寺に持参し、「お焚き上げ」という形で浄火によって天にお還しするのが正式な作法です。
遠方で持参できない場合は、郵送で受け付けてくれる寺社もありますので、事前に確認してみましょう。
御朱印帳という「器」に敬意を払うことは、そこに記された神仏とのご縁そのものに敬意を払うことに他なりません。
最後まで大切に扱うことを心がけましょう。
③御朱印帳を置いてはいけない場所と正しい保管方法
 運気アップ研究所:イメージ
運気アップ研究所:イメージ
神聖な参拝の証である御朱印帳は、保管する場所にも気を配る必要があります。敬意の表れとして、適切な場所に保管しましょう。
理想的な保管場所
最も理想的な保管場所は、自宅の神棚や仏壇です。
これらがない場合は、自身の目線よりも高い、清浄な場所に保管します。
具体的には、本棚の上段や、大切なものをしまうタンスの引き出しなどが適しています。
これは、神仏を見下すことのないようにという敬意の表れです。
逆に、以下のような場所は保管場所としてふさわしくなく、御朱印帳を傷める原因にもなりますので絶対に避けましょう。
避けるべき保管場所
- 床の上や低い場所
神仏を見下すことになり、不敬とされます。 - 不浄な場所
トイレや浴室、ゴミ箱の近くなどは避けましょう。 - 湿気の多い場所
台所や洗面所など。カビや紙の波打ちの原因になります。 - 直射日光が当たる場所
墨や朱印の色褪せを引き起こします。 - 車内のダッシュボードなど
高温になり、著しく御朱印帳を傷めます。
また、持ち運びや長期保管の際は、専用のカバーや袋、伝統的な桐箱(きりばこ)などを活用すると、汚れや湿気、虫害から御朱印帳を守ることができます。
桐は防湿・防虫性に優れ、古くから大切なものを守るために用いられてきました。
④初詣の御朱印が迷惑になるケースとは
 運気アップ研究所:イメージ
運気アップ研究所:イメージ
一年で最も神社仏閣が賑わう初詣の時期。この時期に御朱印をいただくこと自体は問題ありませんが、状況によっては寺社側にとって「迷惑」となってしまうケースがあることを理解しておく必要があります。
主な理由は、圧倒的な混雑と人手不足です。
特に正月三が日は、参拝者の対応に追われ、社務所や授与所は大変な混雑となります。
そのような状況で、一枚一枚手書きする時間のかかる御朱印の対応をすると、長蛇の列ができてしまい、他の参拝者の妨げになったり、寺社側の業務が滞ったりするのです。
このため、多くの寺社では初詣期間中の御朱印対応について、以下のような対策を取っています。
初詣期間中の一般的な御朱印対応
- 書き置きでの対応
あらかじめ紙に書かれた御朱印(書き置き)のみを授与する。御朱印帳への直接の記帳は断られることが多いです。 - 期間をずらしての対応を推奨
松の内(1月7日や15日など地域による)が明けてから、落ち着いた時期に改めて参拝に来るよう呼びかける。 - 授与を休止する
特に小規模な寺社では、期間中の御朱印対応そのものを休止する場合もあります。
「せっかく来たのに書き置きしかもらえなかった」と不満に思うのではなく、寺社側の事情を理解し、その方針に従うのが参拝者としての配慮です。
どうしても手書きの御朱印がいただきたい場合は、混雑する時期を避けて参拝する計画を立てましょう。
⑤御朱印集めとスピリチュアルで目指す運気アップ
 運気アップ研究所:イメージ
運気アップ研究所:イメージ
御朱印集めは、スピリチュアルな観点から見ても、運気アップに繋がる素晴らしい実践となり得ます。
ただし、それは御朱印という「モノ」が持つ力によるものではなく、参拝という「行為」を通じて自身の内面が変化するからです。
神社仏閣は、清浄なエネルギーに満ちたパワースポットです。
そのような場所に定期的に足を運び、心を静めて祈りや感謝を捧げる行為を繰り返すことで、以下のような効果が期待できます。
心身の浄化と精神の安定
日々の生活で溜まったストレスやネガティブな感情が浄化され、心が穏やかになります。
この精神的な安定が、物事を冷静に判断し、ポジティブな選択をする力を与えてくれます。
自己との対話
静かな境内で過ごす時間は、自分自身の内面と向き合う貴重な機会です。
自分の願いや感謝を再確認することで、生きる目的が明確になり、日々の生活に張りが生まれます。
幸運を引き寄せる体質へ
感謝の気持ちを持ち続けることで、物事の良い側面に目が向くようになります。
このポジティブな心の状態が、良いご縁や幸運な出来事を引き寄せやすくするのです。
御朱印は、こうしたスピリチュアルな旅の「大切な記録」であり、「記憶を呼び覚ます鍵」です。
御朱印を見返すたびに、その場所で感じた清らかな気持ちや穏やかな時間を思い出し、心をリセットすることができます。
これが、御朱印集めを通じた真の運気アップの仕組みなのです。
まとめ:御朱印で運気が下がるは本当か?
この記事を通じて明らかになったのは、御朱印そのものに運気を上下させる力はないということです。
御朱印は、それを求める人の心を映し出す鏡のような存在。
最後に、運気を下げるのではなく、豊かなご縁を結ぶためのポイントをまとめます。
- 御朱印で運気が下がるという噂は心構えや行動への警鐘である
- 運気を下げるのは御朱印ではなく不敬な行いそのもの
- 御朱印は商品ではなく神仏への参拝の証
- 参拝せずに御朱印だけを求めるのは本末転倒
- スタンプラリー感覚の収集は神仏への敬意を欠く行為
- 神様と仏様が喧嘩するという俗説は神仏習合の歴史を知らない誤解
- 御朱印帳は危険な物ではなく神聖な器
- 御朱印帳をぞんざいに扱うことが運気を遠ざける
- ご利益はモノではなく参拝というプロセスに宿る
- 作法やマナーを守ることが神仏との良好なご縁に繋がる
- シンプルな御朱印は手抜きではなく寺社の伝統の現れ
- 御朱印帳は神棚や仏壇など敬意を払える高い場所に保管する
- やむを得ず手放す際はお焚き上げをお願いする
- 収集に疲れたら一度立ち止まり参拝の原点に返る
- 御朱印は心を映す鏡であり自身の行いが運気を決める
最後までお読み頂きありがとうございます♪


